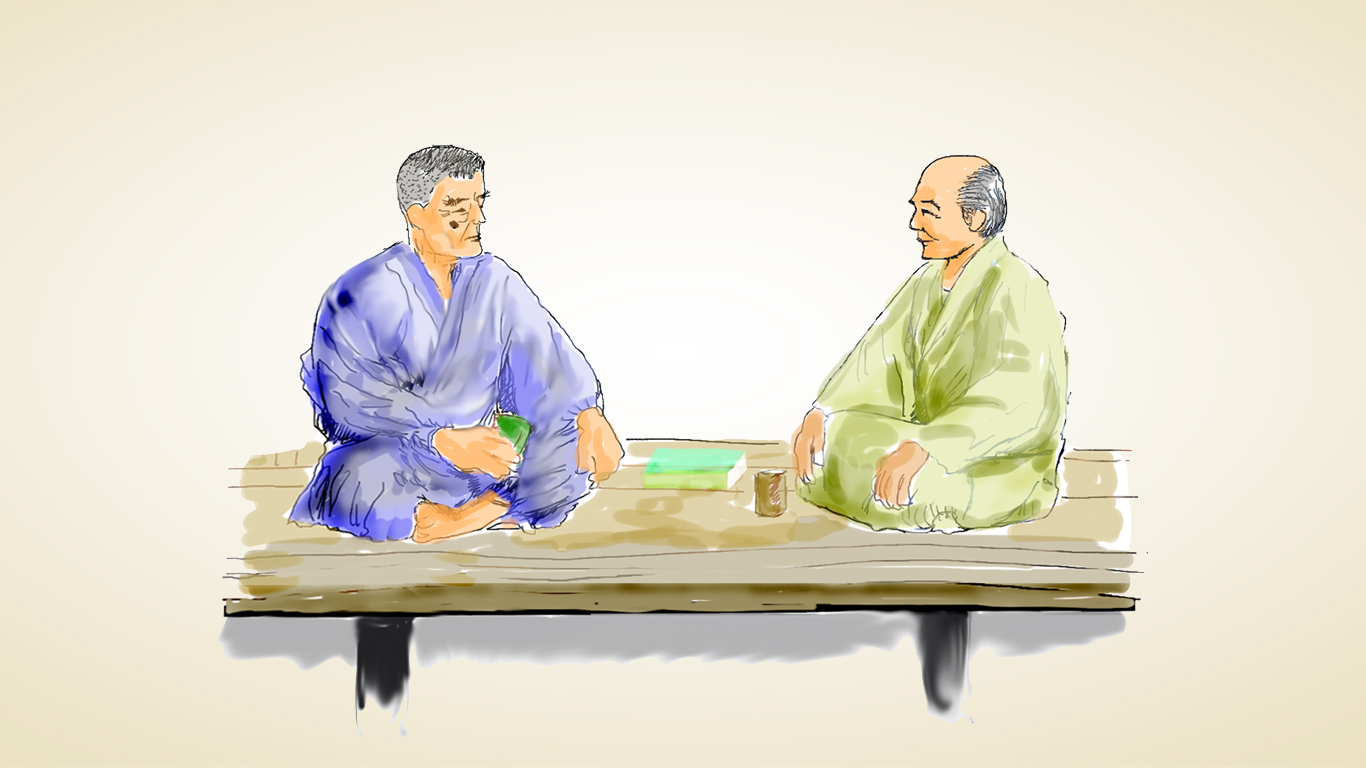
いまの世の中は「愚痴」の似合う世の中のように思います。あれっ? 「そりゃあ、お前の心が愚痴っぽくなっているからじゃあねえか。」という声が聞こえてきました。そうかも知れません。
愚痴 ぐち グチ guchi 愚痴 ぐち グチ guchi 愚痴 ぐち グチ guchi
もう10年も前に「昨日の向こう」という詩集を作った。その詩集の表紙を年賀状の絵柄にした。ちょっとした知り合いの著名な童話作家にその賀状で年賀のご挨拶をした。お返事をいただいた。「素敵な題名の詩集ですね」と書いてあった。 |
|
思い出への道
思い出への入り口は 到着すると静かに霧が晴れるように するとぼくはまるで思い出の発掘調査のように そんな作業をぼくは思い出考古学と言っています |
でも、そうしてできた詩作品は ところで 新潟へ旅をした時に砂浜から佐渡島の島影をみたとき フランソワーズ・サガンの古い小冊子を古本屋で見かけて 今年はどんな道への入り口を行けるのでしょうか |
ところが、そのようにして書いた詩をかなり多くの人が「こんなのは女々しい少女趣味の抒情詩ではないか!」「ロリコン・マザコンの女々しい演歌にすぎないから、現代詩の仲間ではない。三流の素朴派の詩とは言えない作文だ。その証拠に分かり易すぎるだろう?」と言われ続けています。それでも自分を壊すつもりはないので描き続けていますと、もう二十年以上も時が過ぎるのにまだぼくを「ロリコン詩人」だとニヤリと跳ね飛ばすのです。 わけのわからない現代詩なるものを描き続けて、日本の文芸世界から「詩」を暗い倉庫に入れてしまった自称詩人たちの所業に、ぼくは大いに愚痴を言いたいのです。なんども言い続けてきましたが、我が国の「うた」の源を探ってみてください。歌は理屈ではなく心をつなぐ優しくて温かい声だったことを知ってほしいと思います。みんなで歌いみんなで楽しめる文芸こそ真の文芸ではないかと。 で、今年もぼくはぼくの信念を貫くぞという決意を表したくて、このページにその決意を記したわけです。 自らを歌で紹介仕合い、歌で知り合い、歌で互いを認め合い、たくさんのお話や所業を理解しあって心を通わせて、ともに日々を過ごして夫婦になって行った古代の結婚の姿の「歌垣」を知っていますか? 詩は本来そんな歌から生まれたものだと思うのです。 また、その「歌垣」が行われていた時代の、貴族たちの間にも和歌はさかんに作られていてあの著名な「万葉集」など編纂されました。その和歌集の中の大御所の柿本人麻呂さんの「歌(和歌)」も、今の日本の「詩歌」のおおきなルーツの一つです。 太平洋戦争後に生まれた跳ねっ返りの詩人たちの、いまではもう古くなって、カビの生えた「現代詩」なるものを金科玉条のように崇拝している年寄り詩人たちの目を冷まさないと、日本の「詩」は腐ってしまいかねないと思うのですが、いかがでしょうか。
|
|
