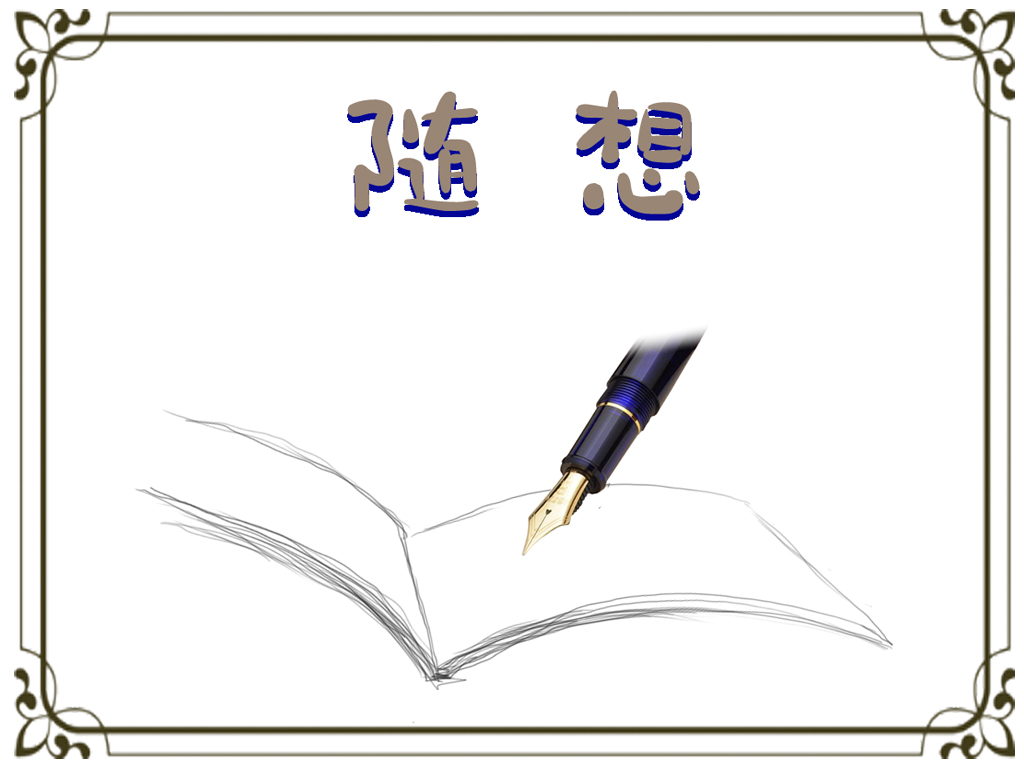涙
ボクの胸の内にはバケツがある
その中には水が入っている
高まる感情の山が
巡ってくるたびに一つのバケツが
込み上げるように胸の内から
眼の出口までせり上がってくる
そこで耐えきれずにひっくり返ると
涙になって目から零れる
今までには
悲しいこと、辛いこと、寂しいことの他に
嬉しい時も、感動した時も
家族や親族や友人たちの喜怒哀楽にも
思わず競り上がってはひっくり返って
なんとたくさんのバケツが
涙を演出しただろう
齢、八十になった今はもう
空っぽのバケツばかりが胸の内に転がっている
密かに一つ、二つ水の入った奴があって
眼の出口まできてひっくり返っても
滅多には眼からは出ないで
おしっこの方に回り込んで
こぼれ落ちているらしい
眼のスイッチも錆びついてなかなか動かないし
涙腺という出口の管も
すっかり詰まっているのだろう
面倒くさくて掃除をサボっているからだ |
もうどんなに胸が揺れ動いても
空のバケツが転がってカラカラとなるばかりだ
それなのに不思議なことがある
温かい心に出会うと
温かい眼差しを向けられると
思わずっていう感じで
ぼくの眼は耐えきれなかったかのように
温かい水滴をこぼしていることがある
なぜだ?
寂しく悲しかった少年時代から青春の時代に
孤独過ぎたぼくが密かに我慢してしまっておいた
とっておきの水差しに入れておいた水
そいつが突然
老いても涸れない泉のように
思わず額まで上がってきて
詰まっているはずの涙腺を無理に染み出すように
眼の出口まで来て
老いて壊れかかった栓を滲み出て零れるのだ
綺麗に澄んだ奴と言いたいのだが
やっぱりボクの人生のように汚れた水滴だ
けれども その零れる一滴に
わずかな温もりがある
一瞬の輝きもある
なぜかぼくはその温もりと輝きこそ
ぼくのほんとうの涙だと思う
恥ずかしいのだが
ちょっとだけ誇りたいと思うときがある
|
訳(わけ)
傘寿を過ぎてびっくりするように、自分の心の成り立ちを理解できる事象に出くわしました。自分のアイデンティティとして自覚している次のことを恥ずかしいながら述べておきます。
・ ひとりぼっちでいることに、「寂しさ」と「心の安らぎ」を覚えること。
・ 自己肯定感にはかなり不感症なのか、人との交わりに適度な距離感覚にはまったく自信がないこと。
・ 人の優しさにはとめどなく涙があふれること。愛されることへの願望を深く感じていること。
ずうっと自分という個体にはこんな性質があったんだと思ってきました。つまり「ぼくはこんな人間で、この性格はぼくの個性なのだ」と信じていたのです。そして、これはとても残酷なことですが、ぼくのこんな一面の匂いを感じるのか、ぼくの詩作品を鑑賞しながらぼくという「人」そのものを揶揄する仲間に出会いました。激しい憤り崖を突き落とされたような落胆を嫌というほどに感じさせられたことが最近ありました。あまりに悔しいので「アイデンティティ」ってことを調べていてわかったことがありました。
ぼくの勝手な解釈なのですが、ごくごく大雑把に「アイデンティティ」って奴を哲学的ではなく、心理学的な雰囲気で解釈するとこんな感じでした。
『ひとつは、ぼくのアイデンティティはぼくの「DNA」の中に潜んでいる傾向である。
もうひとつは、生育歴の中でぼく自身の判断傾向(ぼくのあらゆることへの物差し)が定着している性質である。』
そうして、ぼくの個性が作られてきたのだとずっとずっと思ってきました。
ところが、先に挙げた三つの「・」で示した性質はすべて生育歴の中で作られたもので、人にはある条件の中で生育すると共通の性格が作られるということがわかりました。そしてそれはある種の病変のようなもので、特に「自己肯定感」は矯正できることなのだということがわかりました。
生育過程の中で自己肯定感は「真に愛されているという自覚の中で育つ」ということがわかりました。わかるというよりも思い出を辿ると自分に当てはまるということが納得できました。かといって、ぼくが両親に可愛がられていなかったというのではありません。可愛がられていたという自覚はありますが、戦争後とい社会情勢の中でのことで、あまりにも「一緒だった」という時間が無さ過ぎたのです。そして身近にぼくを愛してくれる誰もいなかったのです。ちいさな同情だけが風のように時折吹いてはおりましたが・・・。
また、「真の孤独感は寂しいという感情の常態化だけではなく、物事の判断に自信が持てないという覚束なさが定着してしまう」ということも学びました。自分を見て大いに納得したのです。
だからでしょう。ぼくは教師として生徒には優しい先生であろうとしていました。これは優しさに飢えていた自分の心から出た努力の方向だったのです。また、人の優しさには心が震えるほどの感動を覚えて、かわいそうな出来事ではなく、人の優しさには幼い頃からたくさん涙を感じてきたのです。この「涙」という詩の作品はそのことをさりげなく言いたかった作品でした。
詩に社会性や哲学的な主張や世間への怒りとか、大いなる賞賛を主張する思いを込めることをぼくはしません。詩でものごとを論じるなんて、おにぎりを箸やスプーン・フォークで食べるようなものです。詩は素手で書くもの、鼻歌でうたうものだとぼくは思っています。
もどる |